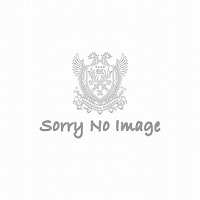横線を引かない。自分の山を登ってみる。
(比較と自己正当化の心理についてメモ)
「あの人は、Youtube登録者数はすごいらしい。すごいなあ。私にも、そんな才能があったらなぁ。」
「あの人は、資産家の家に生まれて、何億円もの資産があるらしい。いいなぁ。そんな家柄に生まれて…。」
「あの人は、業界では有名な一流企業の社長らしい。私にもカリスマ性があったらなぁ…。」
誰の心の中にも、こういう気持ちはゼロではないと思います。
人はつい、他人の成功を 「特別な条件があるから」「有利な環境がそろっているから」 と説明したくなる。
その瞬間、相手と自分との間に、一本の横線を引いてしまうのではないでしょうか。
「あの人には才能がある。横線。私にはない。」
この横線を引いた瞬間、
「その線を超えない前提」を、
自分の中に作ってしまっている気がします。
線のこちら側で立ち止まる人たち
ビジネスの世界でも、似たような構造が見られます。
「あの会社はデザインの才能がある社員が多い。うちはセンスがないから、地味にやるしかない。」
「あの会社は大手の資本が入っている。うちはお金がないから広告なんて打てない。」
「あの社長は有名コンサル出身で人脈がある。うちは無名だから、細々とやるしかない。」
これらは一見もっともらしく聞こえますが、
実は “比較 → 言い訳 → 正当化” の三段跳びです。
実は “比較 → 言い訳 → 正当化” の三段跳びです。
いわば ネガティブ・ホップ・ステップ・ジャンプ。
- 他人の成功を「特別な条件がある」と理由づける。
-
自分の不遇を「仕方がない」と言い訳する。
-
結果として「今の状態を続けるしかない」と正当化する。
こうして、横線のこちら側で立ち止まってしまう会社も、少なくありません。
線を引くのではなく、地形を歩く
けれど、本当は――
「あの人は、資産家の家に生まれて、何億円もの資産があるらしい。まあ、それはそれで別に構わない。」
そう思えばいい。
なぜなら、同じ山に登る必要はないからです。
人にはそれぞれ違う山がある。
登るルートも、歩く速度も、眺める景色も違う。
「線を引く」代わりに、「地形を歩く」。
自分のいる場所の地形を見極め、 違う頂上へ、どんな角度から登ればいいかを考える。
それが、本当の比較の使い方です。
1.比較ではなくポジション
「あの人は曲を作る才能がある。自分にはそんな才能ないから、地道に働くしかない。」
そう思った瞬間、人は横線を引いてしまう。
でも、本当に「別の山」に登ればいい。
音楽をつくる才能がなくても、音を伝える・構成する・演出する・分析する側に立つことはできる。
「創る人」ではなく「響かせる人」としてのポジションを設計するのも良い選択だと思う。
同じ土俵で戦う必要はない。
才能の差を嘆くよりも、 どの角度から関わるかを設計する力こそが、ビジネスの武器になる。
2.資本は、お金だけではない
「あの人は資産家の家に生まれて、何億もある。いいなぁ、そんな家柄に生まれて…。」
確かに、お金は大きな力です。
でも、それだけが資本ではありません。
お金がなくても、お金のある人にはできない勝ち方がある。
-
人脈という資本
-
知恵・知識という資本
-
人と人とをつなぐ調整力という資本
-
技術力という資本
これらを資本と考えても良いと思います。
それは、資金では買えない資本です。
でももし、お金(資金)が必要なら、クラウドファンディングや提携など、 仕組みをつくって集める発想もある。
どのように「立ち回るか?」によって、資本はいらなくなることも多いです。
「自分はどんな資本構造で勝負するか」を設計する。 そこから、本当の経営が始まるのではないでしょうか。
3.才能ではなく、構造をつくる
「あの人は一流企業の社長。私にはそんな才能ない。」
そう感じるのは自然です。
でも、才能とは生まれつきのものもありますが、習慣と構造の結果でもあります。
才能のある人は「才能があったから続けた」とも言えるでしょうが、
「続けたから才能になった」人だって多くいます。
-
その人がどんな習慣・環境・仕組みで成果を出しているのかを観察する。
-
そこから自社で再現できる構造を抽出する。
-
才能の代わりに、仕組みを味方につける。
つまり、「才能を羨む」よりも、
「その才能を支えている構造を見抜く」ことが、次の一手になると思うんです。
線を引かない。自分の地形を見る。
比較とは、他人を見て落ち込むためのものではなく、 自分の位置を把握するための地図だと思います。
他人の条件を羨むのではなく、 自分の条件を前提に戦略を考えること。
「比べても仕方がない」ではなく、
「比べた上で、じゃあ自分はどうするか」と問い直す。
そして、制約を言い訳にするのではなく、
「その条件なら何ができるのか」を探してみたいです。
それこそが、経営者の思考だと考えます。