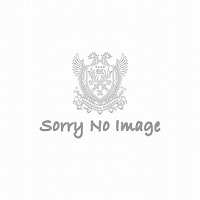先日、あるクライアントさんから、こんなメールをもらいました。
「経済の仕組みも変わると言われている、誰もが判断できないような変革の時に、
佐藤先生は、こうした戦国のようにも見える時代を迎えているとしたら、どんな考えなのか知りたいと思いメールしました。」
率直に言って、すごく本質的な問いだと思いました。
もしかしたら、同じようなことを感じている人も少なくないと思ったんです。
確かに、ビジネスを取り巻く変化のスピードが大きくて、激変しているかのように感じている人もいるかも知れません。
本当に変化が激しいのかどうかは別として、私自身のためにも、頭を整理したいと思い、まとめることにしました。
参考になれば幸いです。
時代の現状認識
AI、経済、価値観、働き方、すべてが変化していて、しかもそのスピードが異常に速まっていると感じます。
ただし、世の中は常に変化しています。
ビジネスの競争は、いつも戦国時代のように激しく競争しあっています。
ただ、私達は年齢的にも、もっと変化がゆっくりの時代にビジネスをしているので、今の時代のことを、相対的に早く感じるのかも知れません。
もう変化のスピードは遅くはならないと思います。
今は「この変化についていけない」と言っている人もいますが、まだ激しくなるだろうし、まだスピードは早まると思います。
ただ、繰り返しになりますが、こうした変革・変化の時代というのは、いまに始まったことではありません。
■ 流れを読む、ということ
「戦国の世」も、きっと当時の人達からしてみれば、激変の時代だったに違いありません。
戦国の時代を生きたリーダーたちは、
ただ戦っていたのではなく、“時代の流れ”を読んで動いていました。
信長は、戦いの才能もありましたが「構造を読む力」がすごかったと思います。
“戦国から商業の時代へ”という流れを早く掴み、増大する軍事費をまかない、経済力をもって優位になりました。
経済力があり、新しい鉄砲という兵器を持ち、斬新な戦術と組み合わせて天下統一を目指した。
秀吉は、人々の心を読んで、利用するのが上手だった。
いつ自分の土地や命が奪われるかわからない不安定な時代に、「これ以上戦う必要はない、平和な世が来た」と印象づけた。
「能力と努力次第で、身分を超えて最高の地位に就くこともできる」と自分の出世が説得力をもっていました。
そこから時代は過ぎても、やっぱり時代のリーダーは同じように流れを読んでいました。
松下幸之助さんの経営哲学は、アメリカ型の合理性、効率性、そして大衆市場を志向する資本主義を取り入れていました。
それだけではなく、日本古来の「和の精神」や人間性を重視する価値観を融合させて成功しました。大量生産の時代が来ると流れを読んで、状況を活かして活躍していくんです。
ここで、共通点
彼らに共通していたのは、「時代を読む」「流れを読む」のが得意だったというだけではありません。
自分の価値観の軸や、自分の持ち味についても理解して活用していたと思います。
例えば、松下幸之助さんです。
松下幸之助さんと同時代、またはそれ以前から、「和の精神」や「人間尊重」を重視した経営の思想は存在し、実践されていました。
でも、「わかりやすく伝え続ける能力」、そしてそれを組織の隅々まで行き渡らせる「工夫(ツール)」は、松下幸之助さんの決定的な持ち味であり、他の哲人経営者とのスケールにおける最大の違いだと思います。
1.誰でも理解できる「言葉のちから」
2.伝えるための工夫・ツール(手帳、機関誌、書籍など)
伝え続ける能力を発揮して、巨大企業グループの精神的な支柱になっていったんだと思います。
それが持ち味であり、その持ち味を活かしきったのだと思うんです。
つまり、いつの時代でも、
「流れを読み、己軸を持ち、己軸に従って最適なポジションを選び、状況を活かして生き残る。
そして、生き残るだけでなく、流れを追い風に変えて躍進する。」
大事なのは、これだと思います。
確かに、変化が止まらない時代です。
でも、全然、それを恐れる必要はないと思っています。
我々が、これまでやってきたように、
「流れを読む。己軸・持ち味を持つ。そして、持ち味を活かして、流れを追い風に変える。」
それをやっていくだけだと思っています。
コンパクトに伝えるのは難しいけれど、自分の頭の整理のためにも言語化してみました。
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただいてありがとうございます。
ではまた